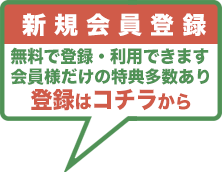空き家は、お金と時間と労力がかかるのでほっておけない。
古い建物のご相談で、空き家の処分に困られている方が多くいらっしゃいますね。
「親の空き家をもっているが、相続までまっていても、
お金がかかるばっかりでどうしようもないし、管理するのも大変、
ただ、古すぎて売れそうもないし・・・」
というものですね。
じゃぁ、ほっておこうということになるのが一般的ですが、
いずれその問題は再燃します。
やっぱり、うまく解決したいですよね。
空き家になっている多くの原因は、
古い住宅を建てたままにしている方が、
固定資産税が安く済むからということもあります。
神戸市での住宅150㎡の土地で、1500万円の評価額の場合、
住宅用地であれば、35000円ぐらいですが、更地になれば、
210,000円ぐらいに跳ね上がります。
これは、あまりに負担がことなりますので、やはり、手がつけられません。
しかし、今後もずっと、そのままというわけにはいかなくなるようです。
じつは、平成26年秋の臨時国会において空き家対策推進特別措置法が成立いたしました。
この法律により全国の自治体が放置空き家の所有者に対して積極的に関与できるようになります。

ほったらかしにできない世の中に変わりそうです。
空き家といっても、なかなか簡単に分類できるものではないのですが、この法案では、
空き家は、「空家等」と「特定空家等」の二つに分類されます。
「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいいます。
そして、特定空家等に対しては、建物の除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の指導・助言、勧告、
そして、命令を出すことが可能となります。
つまり、汚くしている方は、更地にしてね、ってことですね。
そうすると、土地に対する住宅用地の緩和がへります。
固定資産税は課税標準額が6倍に跳ね上がりますね。
こうなると、住宅として活用するか、
解体して利用するか、何かに貸すか、しかないわけですね。
もちろん、解体するにもお金がかかるし、
住宅として活用するためにも、リフォームやなんやらでお金がかかります。
建替えしようものならもっとですよね。
さぁ、どうしようということで、相談窓口を探したくなるものです。
空き家相談が今後地域で整備され、一部、建物調査の助成があります。
こういった相談窓口は、各市町村におかれています。
そして、今後もっと充実していくように思われます。
もちろん、空き家バンクなどが整備されていたり、、
移住者支援をされるなど積極的な市町村もありますが、
老朽化の酷い建物だけ相談にのる市町村もあります。
兵庫既存住宅活性協議会という団体では、
兵庫県内の空き家相談窓口の設置のために、
平成26年11月25日より、相談員をトライアルで待機させて無料相談をうけつけています。
建物を解体すべきか、住宅として利用できるのか、その後、
どのぐらいで貸せるのか?売れるのか?
建築士・解体会社・宅建業者からの適切な意見をきくため、
ある限定された戸数については、無料で建物の調査をおこなって、
適切な相談につなげようとしています。
たとえば、耐震改修工事をして、再度住宅としての再活用するにあたり、
耐震改修工事の補助金の活用提案をしたり、その後の賃貸活用や、
また、それによる固定資産税の減額措置の情報提供もします。
新築や長期優良住宅に建て替えた場合でも、
固定資産税の減額措置もありますね。
もちろん、金額にこだわらず処分されるのであれば、
ただ、早く売却することをお奨めします。
しかし、せっかくの住まいという資産を、
できれば、未来のために上手にいかしたいですよね。
今後も、空き家対策関連には、さまざまな助成金や、
地域の制度などが拡充されるでしょうから、注目しておきましょう。